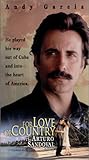
For Love Or Country: Arturo Sandoval Story [VHS] [Import]
キューバの伝説のトランペット奏者Arturo Sandoval(アルトゥーロ・サンドバル)の“自伝”。
基本的に反革命の映画。 特に80年代以降CUBAを離れていった人々の心境の変化をよく描き出していました。 <アルトゥーロの奥さん・マリア・エレーラ>を通じて我々はその気持ちを汲み取ることができます。「私が外国人を招いたり、主人が好きな音楽を演奏しただけで壊れるような革命ですか? その程度ならやめたら?」というセリフが印象に残ります。
実際のアルトゥーロ・サンドバルはCUBAでカストロ兄弟の次に高級車を乗り回して、豪奢な生活をしていたそうです。 したがって、アンディ・ガルシア演じるところの人物とはかなり違うのだということを実際にアルトゥーロを知る人物から聞きました。 それがトランペット奏者としての彼の価値を貶めるものではありませんが。 どうしても映画には脚色が付き物ですし、ドラマティックにしないと観客を呼べませんからね。 実在の人物と切り離して見なければならないけれども、非常に興味深い作品です。

Cronica de una muerte anunciada (Vintage Espanol)
「何故サンチャゴナサールは殺されたのか?」それがこの作品の主題である。
忘れ去られた村で、30年前に起こった殺人は、偶然と必然が組み重なって起ったものである。被害者の友人であり、加害者のいとこである主人公が、その謎を解こうとすればするほど、理解不能になっていく。
彼が殺された理由は「花嫁の貞節を奪った」からだが、誰もそれを信じず、彼を殺した理由は「妹(花嫁)の名誉を守る為」だったが、本気で殺そうとは思っておらず、だから周りに吹聴して実行が中断される事を願っていたが、誰もそれを止められなかった。
よそ者であった被害者と、同じくよそ者であった花婿、この二人がこの閉鎖された村で起った事件の被害者ともいえる。
彼らが、「神の前でも無罪」と言ったのは、自己の意思に反した犯罪は神の意志としてしか考えられないからであろう。それほど多くの偶然が重なり、この「予告された」殺人が決行されてしまった。
不思議な小説である。読めば読むほど、「殺人が起きた理由」から遠ざかっていく。こうした理論的な手法をとりながら、この様な印象を与え迷宮に誘うような印象を与える作者の技量はさすがである。

愛その他の悪霊について
「ガルシア・マルケス全小説」と銘打った作品群のうち、既刊のものとしては、『コレラの時代の愛』(1985年)と『わが悲しき娼婦たちの思い出』(2004年)の間に発表された作品です(1994年発表)。第二代カサドゥエロ公爵の娘で、母ベルナルダの娘に対する嫌悪のために土着民の女中たちのなかで育てられたシエルバ・マリア・デ・トードス・ロス・アンヘレス(「全ての天使の僕マリア」の意)と、教区神父カエターノ・アルシーノ・デル・エスピリトゥ・サント・デラウラの間の、愛の失墜を描いた物語です。
悪霊憑きと呼ばれるシエルバ・マリアと聖職者であるカエターノ、聖俗の両極端にある二人の間の愛は、人々が聖と俗と名付けたに過ぎない概念による翻弄、それに対する戦いを経て、失墜へと到ることになります。それはまた、コロンビアという国における宗教、社会制度、俗習による悲劇とも呼べるかもしれません。
マルケスの作品、特に『族長の秋』以前の作品は、混沌と明晰が同居した独特のドラマツルギーを大きな特徴としていましたが、『コレラの時代の愛』以降は、混沌に対する明晰の比重が増してきたように見受けられます。そして、更に饒舌さを増した語り口は、この物語を紐解いた読者を物語の終焉(マルケスの作品に終焉というものがあるとすればですが)へと引き付けて止みません。
現在80歳のマルケスがこの先物す作品は多くはないでしょうが、今尚作家としての熟成が進むこの稀有な作家の新作が待たれます。
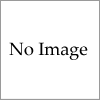
キューバの伝説のトランペット奏者Arturo Sandoval(アルトゥーロ・サンドバル)の“自伝”。
基本的に反革命の映画。 特に80年代以降CUBAを離れていった人々の心境の変化をよく描き出していました。 <アルトゥーロの奥さん・マリア・エレーラ>を通じて我々はその気持ちを汲み取ることができます。「私が外国人を招いたり、主人が好きな音楽を演奏しただけで壊れるような革命ですか? その程度ならやめたら?」というセリフが印象に残ります。
実際のアルトゥーロ・サンドバルはCUBAでカストロ兄弟の次に高級車を乗り回して、豪奢な生活をしていたそうです。 したがって、アンディ・ガルシア演じるところの人物とはかなり違うのだということを実際にアルトゥーロを知る人物から聞きました。 それがトランペット奏者としての彼の価値を貶めるものではありませんが。 どうしても映画には脚色が付き物ですし、ドラマティックにしないと観客を呼べませんからね。 実在の人物と切り離して見なければならないけれども、非常に興味深い作品です。
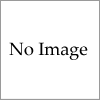
青い犬の目―死をめぐる11の短篇 (福武文庫)
単行本刊行は1990年、文庫本第1刷は94年、短篇集。ガルシア=マルケスを知ったのは筒井康隆がラテンアメリカ文学をほめていたことからだったと記憶している。「三度目の諦め」は不思議な味わい。語り手は誰なのか、死んだ人か、第三者か、薄れゆく意識なのか。独特の閉鎖空間が味わえる。訳も日本語として違和感なく物語に入れる。マルケスを読んでいると江崎誠致著「ルソンの谷間」に収録されている「岩棚」を思い出した。こういう物語を書きたくなる人というのは国を問わず少なからずいるのだなあ、と思う。「マコンドに降る雨を見たイザベルの独白」は雨降り続きという設定をシュールに感じさせない著者のうまさがでている。




![Hi-STANDARD - Stay Gold [OFFICIAL MUSIC VIDEO] Hi-STANDARD](http://img.youtube.com/vi/scqDV8X5-Xk/3.jpg)


