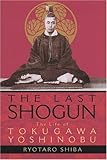
The Last Shogun: The Life of Tokugawa Yoshinobu
この本の原作を読んでいますので、英語力に難のある私でも本書を読めました。概ね面白くはあったのですが、違和感が結構ありました。そして、この違和感が減点の理由です。
まず、慶喜公を「Keiki」と記していること。一説によれば、「Yoshinobu」よりも「Keiki」と呼ばれることを、慶喜公自身が好んでいたとはあるものの、「Yoshinobu」が一般的なのではないだろうかと。どうも、読んでいて引っかかります。
次に、慶喜公の粋な科白の言回しが、平凡な訳になっていること。並みの翻訳者では、日本の尊敬語あるいは謙譲語を上手く訳せないのは仕方がないことですか。例えば、「As long as I,Keiki,am here,and as long as I am protector of His Majesty's person,you may be assure there is no need for alarm.」(原作:「慶喜がこれにあり、玉体守護し奉るかぎり、御心配無用とおぼしめせ」)などは、「うーん」と首をひねってしまいます。味のある科白の妙味が、なくなっちまってます。他にも違和感がある箇所はありますが、いちいち挙げません。
一方で、冒頭に登場人物の紹介や、徳川家の系図があったり、それが案外詳しかったりするので、そこは感心しますけれど。
まあ、時間のある方にはお薦めです。

坂の上の雲〈3〉 (文春文庫)
いよいよ日露戦争の戦いの火蓋が切られる第3巻。
前半部分では、戦争回避の努力もむなしくロシア側の理不尽な要求に追い詰められ開戦せざるをえなくなったプロセスが描かれています。当時の日本にとって大国ロシアと戦うことがどれだけ困難(無謀)なことだったかを思うと、大国から屈辱的外交を強いられた憤りを感じます。
中盤以降は日露戦争準備から緒戦まで描かれていますが、私が印象に残ったのは、さまざまな点で後の日中戦争、太平洋戦争との対比やそれらへの影響が垣間見えたことです。
例えば、開戦の段階で陸・海軍と政府があらかじめ戦争終結に向けたシナリオ(短期決戦での勝利で列強諸国に仲介してもらうこと)を共有化していたことは、昭和の戦争とは対照的で興味深いです。
一方、兵士個々人の闘争心や忠誠心に頼る白兵戦中心の戦闘、補給に対する意識不足など日本軍の特徴がすでにみられ、日露戦争の反省があれば昭和の戦争はもう少し違ったものになったのではないでしょうか。

坂の上の雲〈2〉 (文春文庫)
この巻では主に、闘病しながら文筆活動を続ける正岡子規と、軍人として活躍を始める秋山真之を中心に描かれています。
正岡子規に関して小学校の教科書レベルでしか知らなかったので、過去の俳句や短歌を検証し、新たな作風を作り上げていった彼の功績を初めて知りました。それにもまして結核を患いながらも壮絶なまでに創作活動を行う彼の執念に胸を打たれます。
一方、秋山真之という人物の資質は、欧米に追いつき追い越そうとする明治日本になくてはならないもののように感じます。「飛ぶが如く」で描かれた大久保利通もそうでしたが、この時代には物事に強烈なこだわりをもった人物が必要だったのでしょう。
なお、この巻の最後の章は、ロシアに関する記述になっていますが、欧米でもなくアジアでもないロシアという国の性格が見事に表現されていて、大変ためになります。先に「菜の花の沖」を読んでおけば更に楽しめると思います。

世に棲む日日〈1〉 (文春文庫)
長州。この言葉に何を感じるでしょうか。物語は、司馬さんが、山口県の萩をタクシーに乗ってその空気を感じるところから始まります。明治維新は、長州という書生のような跳ね返りの人々を抜きにして成り立ちません。長州というテコを利用して薩摩は回天の偉業を目指します。この作品は、吉田松陰という思想家から、高杉晋作というまさにその瞬間だけの為に天から命を与えられたような人物が次から次へと世に出て、時代を進めてゆく「長州」という国を描いています。この続編には、大村益次郎を描いた花神が相当するでしょう。明治維新では、長州というユニークな国があり実はその国を作ったのは、徳川の時代であったという面白さ。司馬史観が歴史的な位置付けを与えます。一つの時代と時代の世相を描いた作品であると思います。








